営業のごあんない
- 介護保険制度の仕組み
- 介護保険制度の対象となる方は
- 介護保険の利用手続
- 介護保険制度による福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
- 介護保険制度による福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護保険制度による住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給
- 高齢者の権利擁護・年金・医療・住宅に関する制度など
- 京都市重度障害者住宅環境整備費助成(いきいきハウジングリフォーム)
- 関連情報リンク
介護保険制度の仕組み
介護保険制度では、高齢者の介護費用を、国・地方自治体と国民がそれぞれ負担します。原則として40歳以上の方は、すべて加入を義務づけられています。
京都市の介護保険は、高齢者の介護費用を国・京都府・京都市による公費(税金など)と、40歳以上の皆様に納めていただく保険料を財源として京都市(保険者)が運営しています。
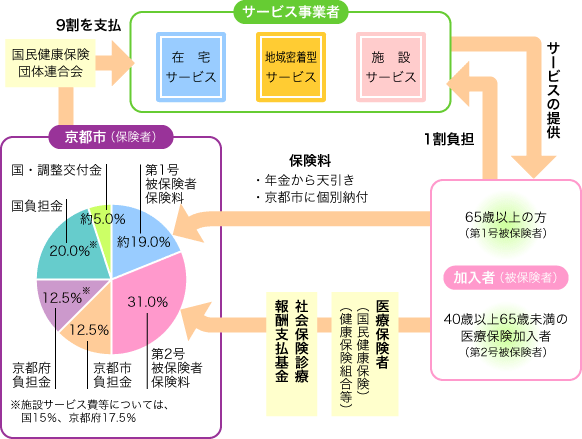
介護保険制度の対象となる方は
介護保険の被保険者となる方、介護サービスを利用できる方は次のとおりです。なお、原則として介護保険に加入するための手続は必要ありません。
■サービスを利用できる方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
- 寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常的動作について常に介護が必要な方
- 家事などの日常生活行為に支援が必要な方
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
- 初老期の認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護・支援が必要な方
■外国籍の方は?
次のいずれかに該当する場合は、京都市が運営する介護保険の被保険者になります。
- 京都市に外国人登録している方で、入国時に決定された入国当初の在留期間が1年以上の方
- 入国当初の在留期間が1年未満であっても、京都市に外国人登録をし、入国時において入国目的などから1年以上日本に滞在すると認められる方
■特定疾病とは?
第2号被保険者がサービスを利用するには、次の16種類の病気(=特定疾病)に該当することが必要です。
- がん末期(平成18年4月から)
- 関節リウマチ*
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患*
- 脊髄小脳変性症*
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症*
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
*平成18年4月に、区分や名称の見直しが行われました。
介護保険の利用手続
介護保険のサービスを利用するためには、申請をして「要介護認定」を受ける必要があります。
お住まいの区の区役所・支所福祉介護課等で申請してください。
■申請を行う方
- ご本人又はご家族
- 地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
■申請に必要な書類
- 要介護認定等申請書
- 介護保険被保険者証
- 「老人保健法医療受給者証」付き健康手帳
- 公費医療証
- 医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
※3、4、5は写し可、3、4はお持ちの方のみ。
2 訪問調査
調査員が家庭などを訪れ、心身の状態などについておうかがいします。
3 かかりつけ医の意見書
かかりつけ医がおられない場合は、医療機関を紹介しますので、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課等でご相談ください。
4 審査・判定
(京都市介護認定審査会)
介護を必要とするかどうか、また、どの程度の介護を必要とするかなどについて、審査・判定を行います。
5 認定
要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。要支援・要介護状態の区分に応じて利用できるサービス量や利用限度額などが決められています。
認定結果の通知は、原則として申請から30日以内に通知されます。
※認定結果などに不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
|
要支援1 |
要支援2 |
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|
非該当(自立) |
|---|
|
|
|
|
|
|
6 要支援1・2の方
介護予防サービス計画の作成(地域包括支援センター=介護予防支援事務所) |
6 要介護1〜5の方
介護サービス計画の作成 |
非該当と認定された方介護サービス・介護予防サービスを利用することはできませんが、次の事業を利用できる場合があります。
|
|
|
|
|
7 サービスの提供
介護サービスを提供する事業者から「重要事項説明書」を受け取り、十分説明を受け、契約を結びます。 |
||
|
|
|
|
8 要支援1・2の方
介護予防サービス |
8 要介護1〜5の方
介護サービス |
|
※平成18年3月31日以前に「要支援」の認定を受けられた方は、次回の更新等まで「経過的要介護」とされ、原則としてこれまでと同様のサービスをご利用いただけます。
介護保険制度による
福祉用具貸与(要介護1〜5の方)・
介護予防福祉用具貸与(要支援1・2の方)
心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支障がある場合に、自宅で過ごしやすくするための福祉用具や機能訓練のための福祉用具を借りることができます。
■都道府県指定の事業者が貸し出しを行います。
■貸与種目
- 車いす※
- 車いす付属品※
- 特殊寝台※
- 特殊寝台付属品※
- 床ずれ防止用具※
- 体位変換器※
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器※
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)※
※要支援1・2及び要介護1の方は、平成18年4月から一定の場合を除き、給付対象外となります。
■利用料
- 福祉用具貸与にかかる費用は、各事業所がそれぞれ設定します。
- 利用者の自己負担額は、それぞれの費用の1割です。
※ケースによって対応が異なる場合もありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
介護保険制度による
福祉用具購入費(要介護1〜5の方)・
介護予防福祉用具購入費(要支援1・2の方)の支給
直接肌に触れて使用する入浴用や排せつ用の用具など、貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)について、購入費の9割が支給します(1割は自己負担)。
■平成18年4月から都道府県指定の事業者で購入された場合に支給対象となります。
■支給対象となる福祉用具
以下の5種目と定められています。該当しない場合は、9割分の支給はできませんので、購入する前に、担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の地域包括支援センター、お住まいの区の区役所・支障福祉介護課等にお問い合わせください。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
■支給申請に必要な書類
- 申請書
- 被保険者証
- 領収証
- 購入した福祉用具を確認できるパンフレット類
- 購入が必要な理由書(通常、ケアマネジャーなどが作成します)
■支給方法
いったん費用の全額をお支払いいだたき、申請に基づき審査を行い、自己負担分(1割分)を除く9割分を保険から支給します。
■限度額
支給の対象となる購入費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、年間10万円です(支給額は9万円まで)。10万円を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担になります。
※ケースによって対応が異なる場合もありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
介護保険制度による
住宅改修費(要介護1〜5の方)・
介護予防住宅改修費(要支援1・2の方)の支給
住宅での生活に支障がないよう、手すりの取り付けや段差の解消など、身体状況に配慮した住宅への改修にかかる費用について、その9割が支給します(1割は自己負担になります)。
なお、平成18年4月から、保険給付を受けるためには、工事着工前にお住まいの区の区役所・支所福祉介護課等へ必要書類を提出し、改修内容等について確認を受ける必要があります。
■支給対象となる工事
以下の6種類の工事以外は、9割分の支給はできません。また、工事の着工前に申請が必要となりますので、事前に担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の地域包括支援センターにご相談いただくか、お住まいの区の区役所・支障福祉介護課等にお問い合わせください。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止や円滑に移動するためなどの床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他上記の工事に伴って必要な工事
■工事を行う前に提出が必要な書類
- 申請書
- 被保険者証
- 見積書
- 改修前の写真(日付がはいったもの)
- 住宅改修箇所見取図
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成します)
■工事完了後に必要な書類
- 住宅改修費事前申請確認のお知らせ
- 領収証
- 改修後の写真(日付がはいったもの)
- 工事費内訳書
■支給方法
償還払いと受領委任払いのいずれかを選択して利用できます。
- ◆償還払い
- 工事完了後にいったん費用の全額をお支払いいただいた後、自己負担分(1割分)を除く9割分を保険から支給します。
- ◆受領委任払い
- 工事完了後に利用者は、自己負担分(1割分)のみをお支払いいただきます。保険給付分(9割分)は、利用者から委任を受けた事業者に、市から直接支払います。
■限度額
支給の対象となる改修費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、1住居・1人の認定者あたり20万円です(支給額は18万円まで)。20万円を超える工事の場合、超えた部分は全額自己負担になります。
※ケースによって対応が異なる場合もありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
高齢者の権利擁護・年金・医療・住宅に関する制度など
■成年後見制度
判断力が不十分な認知症の高齢者などに代わり、契約を行ったり財産管理を行うことによって、認知症の高齢者などの権利を守るための制度です。
■内容は
精神上の障害により判断力が不十分な方(認知症の高齢者等)が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に取り消したり、契約の締結などを本人に代わって行う援助者(後見人など)を家庭裁判所が選任することによってこれらの方の権利を守るものです。判断能力が不十分になったときに、親族など(身寄りがない方などは市町村長)が家庭裁判所へ申し立てることにより後見人などが選任される「法定後見制度」と、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ契約を結んでおく「任意後見制度」があります。
■ご相談・お申込みは
法定後見制度:京都家庭裁判所……075-722-7211へ
任意後見制度:京都公証人合同役場……075-231-4338へ
■地域福祉権利擁護事業
認知症の高齢者など(ただし、契約などの内容が理解できる方)が地域で生活されるうえで必要な福祉サービスの利用援助などを行う事業です。
■内容は
(1)情報提供・助言、(2)福祉サービスの利用手続援助(申込み手続の同行、代行、契約締結)、(3)福祉サービス利用料の支払等、(4)苦情解決制度の利用援助、(5)日常的金銭管理サービス
■利用料金は
生活支援員が行うサービスは、1時間1,000円
・生活支援員の自宅から利用者宅までの往復交通費等実費は別途ご負担いただきます。
・通帳、印鑑の保管料は1か月250円。
※詳しくは直接下記までお問い合わせください。
■ご相談・お申込みは
各区社会福祉協議会
京都市社会福祉協議会「あんしん生活支援センター」……075-354-8734へ
■高齢者権利擁護相談
■内容は
高齢者に対する暴力などの身体的虐待、暴言などの心理的虐待、世話の放棄、家族や悪質業者による金銭詐取、施設などにおける身体拘束などの相談に応じます。また、弁護士による法律相談、適切な専門の相談窓口の紹介、センターに併設されているショートステイへの利用調整などを行い、関係機関と連携を図りながら権利侵害の解決に努めます。
■ご相談は
京都市長寿すこやかセンター「高齢者110番」……075-354-8110へ
■高齢者虐待に関する相談
高齢者への虐待の問題に対応するため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)が平成18年4月1日から施行されました。
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の定義が示されるとともに、高齢者虐待を発見した際の通報の義務が定められています。
■高齢者虐待の定義
いずれも高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等の養護者及び介護施設従事者等によるものとします。
- 身体的虐待
- 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること
- 介護・世話の放棄・放任
- 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること
- 心理的虐待
- 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- 性的虐待
- 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
- 経済的虐待
- 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
■通報義務
養護者による高齢者虐待を受け生命又は身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した方は、速やかに通報しなければなりません。また、生命又は身体に重大な危険が生じていなくても、養護者による高齢者虐待を発見した場合は通報するよう努めねばなりません。
■ご相談・お申込みは
これに伴い、高齢者への虐待や養護者の支援に関する相談については、次のとおり受け付けています。
地域包括支援センター 平日9:00〜17:00
各区・支所支援(支援保護)課 平日8:30〜17:00
長寿すこやかセンター(高齢者110番) 平日9:00〜21:30(土曜日含む)、祝・休日9:00〜17:00
■高齢・障害外国籍市民の福祉サービス利用に関する相談
■内容は
言葉や日常生活習慣の違いのために福祉サービスの利用が困難な外国籍の高齢者や障害のある方に対して、外国語の話せる支援員が訪問・電話相談等を行い、福祉サービスの利用を支援します。
■ご相談は
京都外国人高齢者・障害者生活支援ネットワーク・モア……075-681-2721(FAX075-681-2722)へ
京都市重度障害者住宅環境整備費助成
(いきいきハウジングリフォーム)
重度の障害のある方の日常生活を行いやすくするため、また介護にあたる方の負担を軽くするために住宅改造や移動設備の設置を行う場合に、必要な費用の一部が助成されます。
■利用できる人
次の1〜4のすべてに該当する人。
- 住宅改造…身体障害者手帳1級〜2級または療育手帳Aをお持ちの方
移動設備設置…四肢機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちで移動が困難な方 - 原則として、施設や病院に入所・入院中でない方
- 借家の場合、所有者(管理者)から承諾の得られる方
- 生活保護世帯またはご本人及びご本人と同一世帯の方全員(扶養義務者でない方は除く)の前年の所得税合計額が、70万円未満の世帯に属する方
■対象となるリフォーム
対象となるのは、重度の障害のある方本人や介護にあたる方の状況に配慮し、日常生活上のバリアを取り除いたり軽くしたりするリフォームです。
- *住宅改造(例示・身体障害者手帳1級〜2級または療育手帳A)
- (浴室)浴槽の埋込み、滑り止め、手すり、引き戸や折戸への取り替え等
- (トイレ)便器の洋式化、手すり、引き戸やアコーディオンドアへの取り替え等
- (玄関)スロープ、段差解消、引き戸への取り替え等
- (廊下・階段)手すり、滑り止め、足元灯の設置等
- (居室)敷居の段差解消、和室の洋室化等
- *移動設備設置(例示・四肢機能障害1級で移動が困難な方)
- 段差解消機
- 階段昇降機
- 天井走行型リフト
■対象とならないリフォーム
- 住宅の新築、購入または全面改装等に伴って行われるもの
- 家屋の維持・補修
- 日常生活用具給付品目及び設置工事を伴わない福祉機器等の購入費
- 全身性障害者屋内移動設備助成事業により、すでに助成を受けられた方への移動設備設置
- 申請以前に着手または完了しているもの
- 介護保険の給付対象となる福祉用具および住宅改修
■助成額
リフォームに必要な額に助成率を乗じた額。ただし限度額の範囲内、原則として1世帯につき1回限り。
| 世帯区分 | 助成率 | 助成限度額 |
| 生活保護世帯及び所得税非課税世帯 | 100% | 75万円 |
| 所得税課税世帯(税額42,000円以下) | 75% | 60万円 |
| 所得税課税世帯(税額42,001円〜699,999円) | 75% | 50万円 |
日常生活用具または介護保険
|
+ |
いきいきハウジングリフォーム
|
■申請時に用意するもの
- 同居者全員の住民票、または世帯全員の外国人登録証明書
- 所得税がわかる書類(本人および同一世帯の方全員〔扶養義務者でない方は除く〕)
- 印鑑、身体障害者手帳・療育手帳など
■支給方法
工事完了後、助成券に確認印を押して実施業者にわたします。助成費は市から直接事業者に払われます。
■助成までの流れ
相談受付((社)京都市身体障害者団体連合会事務局 TEL075-822-0779)→ 面接相談 → 自宅訪問 → 改善案の検討・作成 → 申請 → 審査・決定 →着工 → 完了報告・検査 → 助成費請求・支払い
※ケースによって対応が異なる場合もありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
ケースによって対応が異なる場合もありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。末尾に記載の関連情報リンクも参考になります。